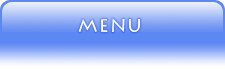| 奇跡の光跡 6 八起正法先生編 |
| 先へ進もう。最初の二日間は徹底して反省であり、残りの八日間は禅定瞑想(反省的瞑想)だった。 そこは長野だが、山一つ越えれば新潟県だ。時々熊が出るらしいが、弟子達は夜十二時になると敷物を持って山へはいり、懐中電灯を照らしながら場所を決めて坐わる。 満天の星に見とれ、午前一時から四時頃まで山中に散って禅定瞑想をするというもので、心を完全に開いて解放し天地間、すべてのものの動きを声と心でキャッチする訓練である。 離れた所にいる信次師が「念」を発し、それを弟子達がキャッチするという訓練であった。 園頭師は次のように言う。「それぞれ、みな離れて座を占めて禅定に入る。禅定瞑想するとなると、多くの人は精神統一することと考えて凝念してしまう。 そうではない。完全に心を解放して、心が何ものにもとらわれない状態になって、天からの啓示を完全に受け、潜在意識の底から湧き上ってくる想念とを、自分の胸の、今の一点において結び合わせるのである。 その時、先生の鞄持ちをしていた二十三、四の青年がいて、禅定の姿勢のままでこっくりこっくり眠ってしまう。 すると集合を命ぜられれ、、懐中電灯で足下を照らしながら、声のする先生の許へ集まる。どすーんと倒れる者もいたが、集まると先生は一人一人にどのように発信したかを尋ねる。 「○○君、いくらぼくが心の扉を叩いても、ぐっすり眠って、眼を覚まさなかったね」、と。 信次師が発した念を、キャッチすることが出来る人も出来ない人もいたが、この修業が夜中の一時から四時まで続き、昼は心の浄化をはかり夜は禅定瞑想をして。九人の弟子達はインドの時と同じ修業をしたのである。 離れた所から送られる想念のキャッチの訓練を、信次師は次のように言っている。 受信機と発信機は人間が製り出したもの、ラジオやテレビは人間がつくったものである。人間の心の中には、その作用がすべて整っている。ただそれを自分が受ける能力を持っているか、いないかだけの問題で、皆さんの心の中が、人を恨(うら)み、妬(ねた)み、謗(そし)る、そして怒る心をつくったり或いは自分自身がより大きな欲望、足ることを忘れ去った欲望が多くなると、心にスモッグが出来てしまい、それが多くなればなる程、盲目となり、その力を閉ざすことになると。そして念の速度は光の速度より速い。 念の世界には時間、空間がない。つまり思えば即の次元である。 現代は、携帯電話などの便利なものがある。故障をしたり電池が切れると無用の長物と化すが、原始人類の初期のころは、五悪(恨み、妬み、謗り、怒り、足ることを知らぬ欲望)が人類の心の中にはなく、人類はお互いに自由にコンタクトできた。 通信だけでなく肉体から抜け出した意識によって見てくることも出来た。電波も届かぬ深海や宇宙の果てから,あの世に至るまでコンタクトできた。 わかりやすく言えば、テレビの海外ライブのような音声ずれもない、時間も空間もない想えば即の念の世界。それはそれは素晴らしいものを人間は自ら持っていた。だが、その能力も五悪の想念によって閉ざしてしまったというのである。 |
| 奇跡の光跡 7 八起正法先生編 |
| 「特別研修といえば、志賀高原のホテル竜王が、何回も使われて」 信次師は言っている、ここは霊域が精妙で良いから、と。 そして、このとき次のことも明らかにしている。昭和天皇は、インドの時のアショカ王、その後のカニシカ王だった。 大変、勇気ある王だ、と。アショカ王は、世界で初めて戦争の放棄宣言をして仏教に帰依した偉大なる王である。 今世紀には、第二次世界大戦の終戦の決定を宣言されたことは不思議であった。 そして、昭和六十三年五月には、ホテル竜王は園頭師の主宰する国際正法協会の全国支部長・連絡所会議が開かれたが、ホテルの主人と奥さんが当時を想い出し、 「高橋先生にサインを頂いた本は大事にしております」と涙ながらに話した。 そして、 「ここで特別研修を受けられた方々も、今はちりぢりになって」、と感慨深そうに園頭師に話している。 また、この特別研修の時、高橋信次師は 「この宇宙には七つの霊圏があり、この地球を中心とした霊圏を指導しているのが、アガシャ系であり、このアガシャ系がいちばん早い速度で、霊的に進歩しつつある」と。 この大宇宙には七種の人間がおり、姿形は地球人と同じで、人間は人間だ、サルから進化したものではないと。 同じく、この時、「世の中は物質文明の時代から霊的文明の時代へと移ってゆく」と言っている。 研修の五日目の夜の休憩の時、信次師は「私の母は、かつてキリストを生み、日蓮を生んだ人だ」と言い残している。 |
| 奇跡の光跡 8 八起正法先生編 |
| (信次師亡後一年の歩み) 信次師は、亡くなるひと月ほど前から、リンゲル注射を打ち続けていた。にもかかわらず、東北の研修会には、家族、側近が懸命に止めるのを聞き入れず 「行かねばならぬ」と無理を押して講演(「高橋師の最後の講演」の項にある)をした。 渡辺泰男氏は、自著にこう書いている。 「特に、この時の『新復活』というご講演は、獅子吼とはこのことをいうのだなあと心に思ったほどの渾身のエネルギーをふりしぼった大講演で、後にも先にも、このような場面にふれたことは、この時だけだと思っている。 ことに、最後の十分間ほどは先生がこのまま光のエネルギーに昇華されてしまうのではないかと思われるほどの迫力だった。 汗は金となり、それが照明でキラキラ輝く。特に右側の頬に大きく金の塊が生じているらしく、口の動き、頬の動きに応じて、ダイヤモンドのように光り輝いて見えたのが印象的でした。 終ってから、講師一同が先生のお部屋にご挨拶にあがった時、右頬についていた金の塊を取って見たら、「Lの字になっていましたよ」とおっしゃった」、と。 そして、昇天の直前のある日のこと 園頭師に、信次師の本を勧め、正法帰依のきっかけをつけたK氏は、こう話す。 「私が、六月のはじめ、自宅の前まで帰って来た時、一人のやせた青年が「Kさん」というのです。誰かと思ったら、高橋先生でした。 「先生はどちらへ」「病院へ行っての帰りです」「どうぞ、おあがり下さい。お茶でも」。 先生は、私の家に一時間半位いらっしやいましたが、「Kさん、こんなに肉体を酷使するんじゃなかった」といって涙をためていらっしゃいました。 高橋先生は私に気持ちを伝えておけば、懇意にする釈迦第一の弟子といわれた舎利弗・園頭先生に伝えてくれると考えられて、それで、わざわざ、自宅とは反対方角の私の家を訪ねられた、これしか考えられません」と話す。わざわざ反対の方角のK氏宅へ。 Kさんの家は病院から北の方角であり、信次師の自宅は病院から南の方角。まったく反対の方角。わざわざ来られたとしか考えられぬというのである。 〈 一九七六(昭和五十一)年六月二十五日、高橋信次師は昇天した 〉 |
| 奇跡の光跡 9 八起正法先生編 |
| 高橋師の著書を出している三宝出版社の、かっての社長の堀田和成氏は、著書にこう書いている。 「死の四カ月ほど前、釈迦に説法とは思いましたが、折に触れて休養なさるようおすすめしました。 そんな時先生は、「わかっています。私の体は私がいちばんよく知っている。だが、やるべきことをやらねば私の役目が果たせなくなってしまう。私はただ、やるだけなのです」と言われます。 先生は死を覚悟されていました。 残された時間をいかに有効に使うか、それだけがお心を支配していたようであります。 「先生のお気持ちはお察しします。しかし、細く長くという言葉もあります。今のお体には休息がいちばんと思います。ゆっくりと体をお休めになってください」私は、先生に繰り返しそう申し上げました。 < 中略> しかし、時すでに遅く、六月二十五日午前十一時二十八分、ご家族の方の見守られるなかで、その短い生涯を終えられるのでした。」 高橋師の奥様である高橋一栄氏は、著書に次のように書いている。 「『さあ、起こしてくれ。上衣を出してくれ。私は行かねばならない。みんなが待っている』主人は、床の中で、そう私に叫び続けます。 自分の体が自由にならないのに、気持ちだけは明日に迫った関西講演に、早や心は飛んでいるようでした。< 中略> しかし、主人はもう何日も物を食べていません。 それどころか東北講演ですっかり体を使い果たし、そのうえ、つい一日前、ある方が八起ビルに訪ねてくるというのでわざわざ出かけて行き、夜の十時すぎまで話し合い、その無理がたたったのでしょう。 <中略> 今にして思えば、あの時の主人は、家族の者の理解を越えたある使命感だけに己れの魂を燃焼させて生きていたと思います。 それから十日余りして主人は昇天しましたが… 『心に法ありて』 |
| 奇跡の光跡 10 八起正法先生編 |
| また、同じく渡辺泰男氏は「私が会社で執務していると、午後二時頃、GLA本部の信次先生の実弟の興和先生から電話がかかってきて、本日午前十一時二十八分に、高橋先生が亡くなられたというのである。 そして明後日から和歌山県の白浜で関西地区の研修会が行われることになっているが、それに私に出席してくれないかという。 おり返し本部に電話したところ<中略> 忙しい葬儀の準備の合間をみて、私は五階に安置されていた先生のご遺体に最後のお別れをさせていただいた。 安らかに目を閉じていらっしゃる先生のお姿を拝しながら、お釈迦様の涅槃とは、このことをいっているのだと。 『ノアの箱舟』 信次師の長女・高橋佳子氏により『真創世記』三巻が出版されている。 これは当初から佳子氏の作ではないともっぱらの評判もあったが、佳子氏自らが霊感を受けて短期間に書かれたということになっていた。 しかし、昭和六十一年『アドベンチャー・八月号』五十四頁に、SF作家の平井和正氏が「『真創世記』は、私が半年ぐらいにわたって書いた」と発表した。 十年目にして真相が明らかとなっている。 この『地獄篇』に、父・信次師についての記述がある。引用文献として問題があったが、父と娘の親子愛の機微には、平井氏といえども創作出来ない、割り込めない部分があったと思う。 その考えに立って一部引用要約を断っておきたい。 回想の父 <前略> その父が、もう自分の肉体に自信がないというのです。 そして、父の喉を食事が通らなくなりました。父は力のかぎりを振りしぼって講演を続け、最後の本になるべき原稿を書き続けました。 その原稿は私の手もとにありますが、父はこの本は世界を動かすものとなるだろうと、言い続けていました。 異様にはれあがって食事もできない不自由な手でペンを執りつづけたのです。<中略> 約束が守れないと知った父は、関西の講演会場の方向へ向けて土下座をしました。 「行けなくて、皆さん申しわけありませ…」涙をポロポロ流して詫びるのです。 六月十八日、死の一週間前、一人では動けなくなった父は、自宅から、浅草の八起ビルへ移りました。 死の三日前になって、父はようやく布団をしいて体を横にし「ああ、やっとオレも病人らしくなったなあ」それが父の感想でした。 脈搏が乱れはじめた時、あと六時間だけ生きてちょうだいと哀願しました。その時、全てが正常にもどり、父は正確に六時間生きつづけました。 そして心臓は停止しました。そのとたん、私が危篤の父と同じ状態になりました。死と同時に肉体を離れた父が、私の中に入ったための現象だったのです。 その夜から、父は私の体を借りて語りはじめました。私の記憶はないのですが、完全に父の口調で、母と語りあい、別れを告げたといいます。 『真創世記・地獄篇』 |
●奇跡の光跡③ に続く
更新情報・おしらせ
【2012年5月6日】更新